
【元文部科学大臣 盛山 正仁 先生インタビュー】未来の選択肢を守るために、教育の中にプレコンセプションケアを
衆議院議員/元文部科学大臣
盛山 正仁
将来の妊娠や健康のために“今の自分を大切にする”という視点を持つプレコンセプションケア。医療や自治体では徐々に広がりを見せていますが、学校教育の中ではまだ十分に取り入れられているとは言えません。今回は、文部科学大臣として教育政策に携わり、現場の声にも向き合ってこられた盛山正仁先生に、教育現場でのプレコンの意義や、若い世代・親世代へのメッセージについてお話を伺いました。
プレコンセプションケアは教育の現場でどのような意義がありますか?
学校教育の中では「プレコンセプションケア」という言葉自体はまだ一般的ではありませんが、保健教育の中で思春期の身体の変化や性についての学びは行われています。大切なことは、自分の身体を理解することが“自分自身を大切にする力”につながるという視点です。将来の生き方や価値観は一人ひとり異なりますが、その選択肢が閉じてしまわないよう、知識として持っておくことが教育の意義であると考えています。
なぜ学生のうちに学ぶ必要があるのでしょうか?
高校生や大学生は、将来について考え始める時期です。すぐに結婚や出産を考える必要はありませんが、知識がないまま時間が過ぎてしまうと、いざ選択したいときに選択肢が狭まってしまうことがあります。学生のうちに知識を身につけることで、選択できる状態をつくることが大切だと考えています。
日本の性教育の現状と、プレコンの位置づけについてどうお考えですか?
日本の性教育については、人、時代によって捉え方が異なります。学習指導要領の枠組みがある中で、どこまで教えるのが適切かという議論は続いています。プレコンは、性教育を拡大するというよりも、将来の健康や生活設計に関わる視点を加えるものと考えています。
男女が一緒に学ぶことの意義はありますか?
妊娠・出産に至る経緯や将来の家庭像など、自分の人生設計にも関わるような部分については、男女共に学ぶ必要があります。男女が共に学ぶことで、お互いを理解し尊重する姿勢が育まれます。一方で、個人的な悩みや不安に関わる内容は、安心して話せる場が必要です。内容に応じて、男女一緒に学ぶ場と、分けて学ぶ場を柔軟に設けることができる環境を整備することが大切です。内容によって調整することが、安心感と理解の両立につながります。
キャリアや学業を優先したい人は、将来の妊娠・出産とどう向き合えばよいですか?
高校生くらいまでであれば、まだ深く考える必要はないかもしれません。
しかし、大学生になると就職や将来の生活について見えるようになり、人によってはパートナーができ、出産について真剣に考える段階に入ることもあるでしょう。結婚をまだ具体的に意識していない段階でも、関係が深まり、妊娠する可能性が現実的になってくる若いカップルは多くいます。そうした方々にとって、「妊娠の仕組み」や「避妊を含めた正しい知識」を理解することは非常に大切だと思います。望まない妊娠を防ぐために、どうすればよいのかを学び、話し合う機会が必要だと感じています。
もちろん、結婚や出産に対する考え方はケースバイケースです。年齢、キャリアの方向性、ライフプランなど、状況によって最適な選択は大きく変わります。そのため、一人ひとりが自分自身と向き合い、パートナーとよく話し合いながら、納得のいく選択をしていくことが大切だと考えています。
親世代ができるサポートにはどのようなものがありますか?
まずは、心身の健康を大切にする習慣を一緒に考えていくことだと思います。
睡眠やバランスの取れた食事を取ろうということはわが子にも話しておりました。私自身、子どもに上手く伝えられたのかというと、決してそうではないと思いますし、反省をする点もあります。
親が価値観を押しつける必要はありませんが、対話の中で“選択肢があること”を共有することが大切です。親も子も、一緒に考え続ける関係でいられれば良いのではないでしょうか。
また現在、若い女性を中心に痩せたいと思う方が非常に増えていると思うのですが、医学的に見たら痩せすぎで不健康だという捉え方もあります。健康管理、栄養管理といったところも親のサポートが必要だと思います。
常に健康に意識を向けながら、自分の生活・人生を送っていくことが大事だということをお伝えしたいです。
保健体育や家庭科にプレコンを盛り込むことの意義は何でしょうか?
保健体育や家庭科の中で、心身の変化やライフステージに関する学びはすでにあります。その中に、将来の健康や妊娠に関わる「プレコン」を自然に組み込むことができれば、特別な教育としてではなく、自分の身体と生き方を考える学びとして定着していくと思います。プレコン教育では、望まないタイミングでの妊娠を防ぐことも大きな目的であると考えます。
そして、子どもを育てるということは、もちろん大変なこともありますが、当然それだけではなく、子どもを育てることで初めて感じる喜びや、子どもを育てることによって親が学ぶことが沢山あります。マイナス面だけと考えることはないと、生徒さんに理解をしていただくことは重要だと思います。
学校現場でプレコンを教える際の課題は何でしょうか?
まず学校現場においては、先生方がどの程度まで正しい知識を理解し、生徒に伝えられるかという点が重要になります。そして同時に欠かせないのが、保護者のご理解です。「なぜ学校でこうした内容を教える必要があるのか」と疑問を持つ保護者の方も、多くいらっしゃいます。こうした点について丁寧に説明し、理解していただきながら進めていくことが求められます。プレコンセプション教育や性教育をどのように学校教育の中に適切に取り入れていくのかは、検討すべき課題が数多くあると感じています。
また、誰が指導を行うのが最適であるかという点も重要です。医師、看護師、助産師、あるいは学校内で知識のある先生など、役割を担っていただく方はさまざま考えられます。場合によっては、医療関係者など外部の専門家に来校してもらい、授業や指導に協力していただくことも必要でしょう。ただし、例えば大阪の生徒に指導するために東京から講師を招くとなると、距離や費用面の負担が大きくなります。そのため、地域の教育委員会と外部の専門家が連携し、地域に根ざした形で授業を進めていける体制づくりをすることが大切だと思います。
自治体と学校教育が連携することにより、どのような効果が生まれますか?
先ほどの話しにもありましたが、地域とのつながりを持ち、地方公共団体と協力しながら進めていくことは非常に重要です。ただし、自治体単独で何でもできるわけではありません。専門家や医療関係者など多様な立場の方々に協力いただき、どのような体制で教育を行うかを整えていくことが大切だと考えています。教育委員会をはじめとした地域の関係者と連携し、自治体が担える役割を最大限に活かしながら、無理なく継続できる形で取り組みを進めていくことが望ましいと思います。
また、性教育やプレコンセプション教育に対して、国民の皆様がどれだけ関心を持ち、必要性を感じられるかも非常に重要なポイントです。「自分自身のこと」、「家族のこと」、「将来の子どもや世代のこと」として捉えられるかどうかで、理解や受け止め方は大きく変わります。今の時代に即した形で、なぜこの教育が必要なのかをわかりやすく伝え、共感を広げていくことが何より大切ではないでしょうか。
若い世代・妊活世代・親世代へメッセージをお願いいたします。
若い世代へ:結婚や出産は、誰かに求められるものではなく、個人の価値観によって選ばれるものです。ただ、将来子どもを望むのであれば、選択肢が閉ざされないよう、身体や妊娠に関する知識を知っておくことは大切です。迷ったり悩んだりすることは自然なことです。その中で、自分が大切にしたい人生を、安心できる人たちとともに考えていければ良いのではないでしょうか。
妊活世代へ:物事には必ずメリットとデメリットがありますので、マイナス面をできるだけ小さくしながら、プラスの価値をどう活かすかが重要になってきます。「もしかして不妊かもしれない」と思った時には、ためらわずに医療機関に相談していただくことも大切ですし、ご夫婦でよく話し合い、必要に応じて生活環境を見直していくことも必要だと思います。
親世代へ:親御さん自身も子育ての中で良い経験・苦労した経験の両方をお持ちでしょう。それらを踏まえて「ここはこうした方がいい」、「自分たちは失敗したので、こうしない方がいい」といった形で、次の世代にアドバイスをして示唆を伝えていくことは、とても意味のあることだと感じています。
最後に
政府としても少子化対策を進めてはいますが、それでも出生率は下がり続けています。状況がすぐに好転するとは期待できません。だからこそ、「意識の変化」が鍵になると考えています。男女がともに家庭を大切にし、協力して子どもを育てていく。そのような家庭生活の価値を改めて見つめ直すことが重要です。
日本では、周囲の親族や地域が協力しながら子どもを育てる文化も根付いており、すべてが遅れているわけではありません。ただし、男女の役割意識や働き方の面では、まだ改善の余地があります。男性にとっても女性にとっても、結婚・出産・子育てが自然な選択肢として受け止められる社会環境をどう整えていくか。これは、これからも模索を続けていくべき大きな課題だと考えています。
妊娠・出産は義務ではなく、人生の中の選択肢のひとつです。知ることは、選択肢を守り、大切にすることにつながります。FCHは、これからも皆さまが自分らしい選択をできる社会を目指し、情報をお届けしてまいります。
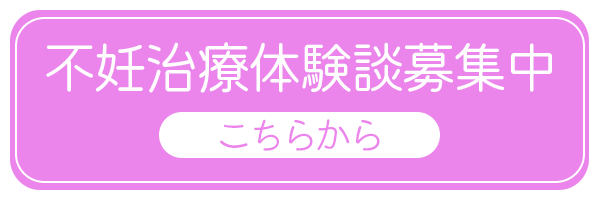
よく読まれている記事

【ニュース】先進医療に「不妊症患者に対するタクロリムス投与療法」が追加

【ニュース・重要】「オビドレル」の出荷停止と今後の見通し

【助成金一覧】東京・神奈川更新のお知らせ

ホームページオープンのご挨拶


 厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ FCHは
FCHは







