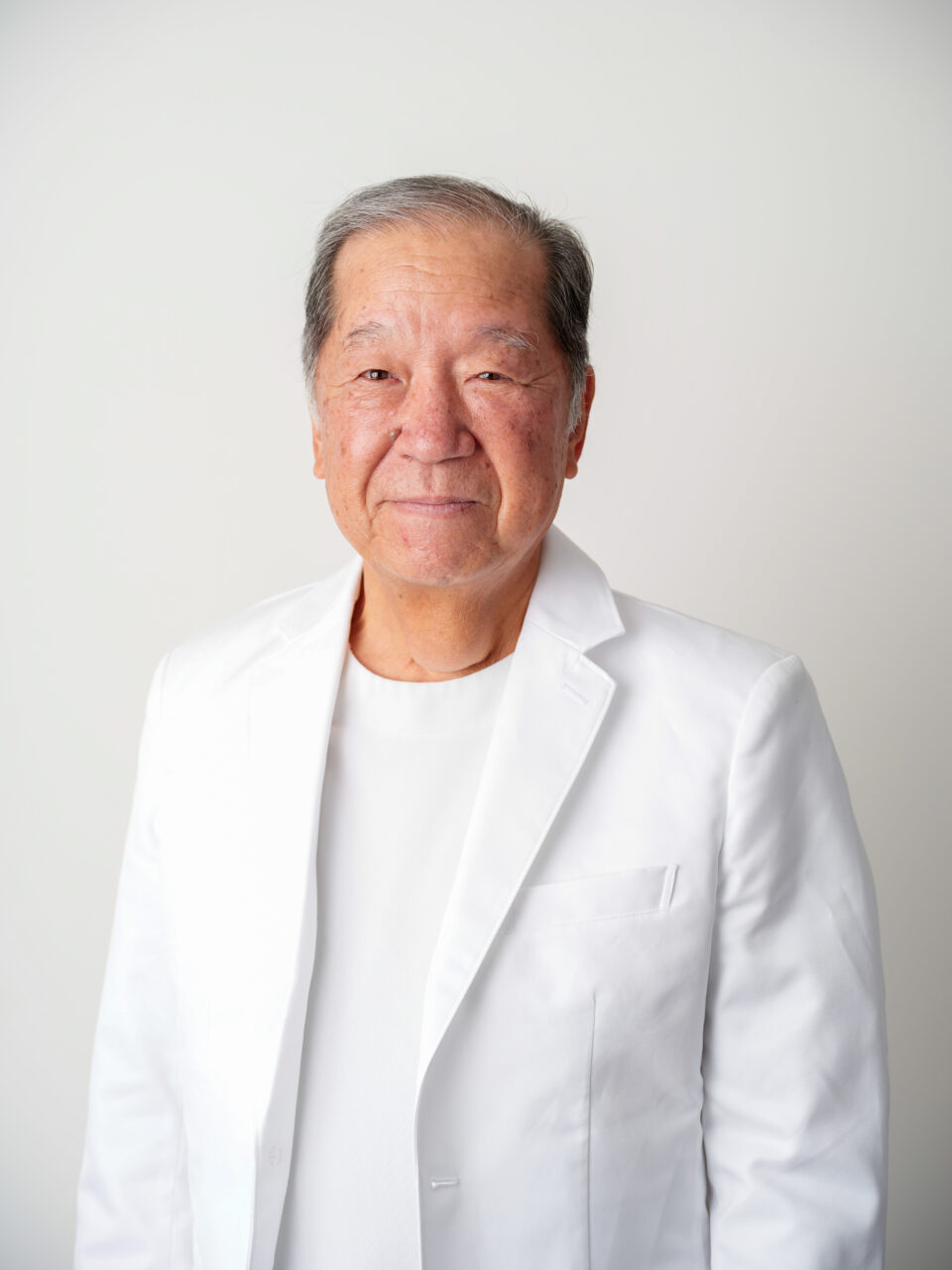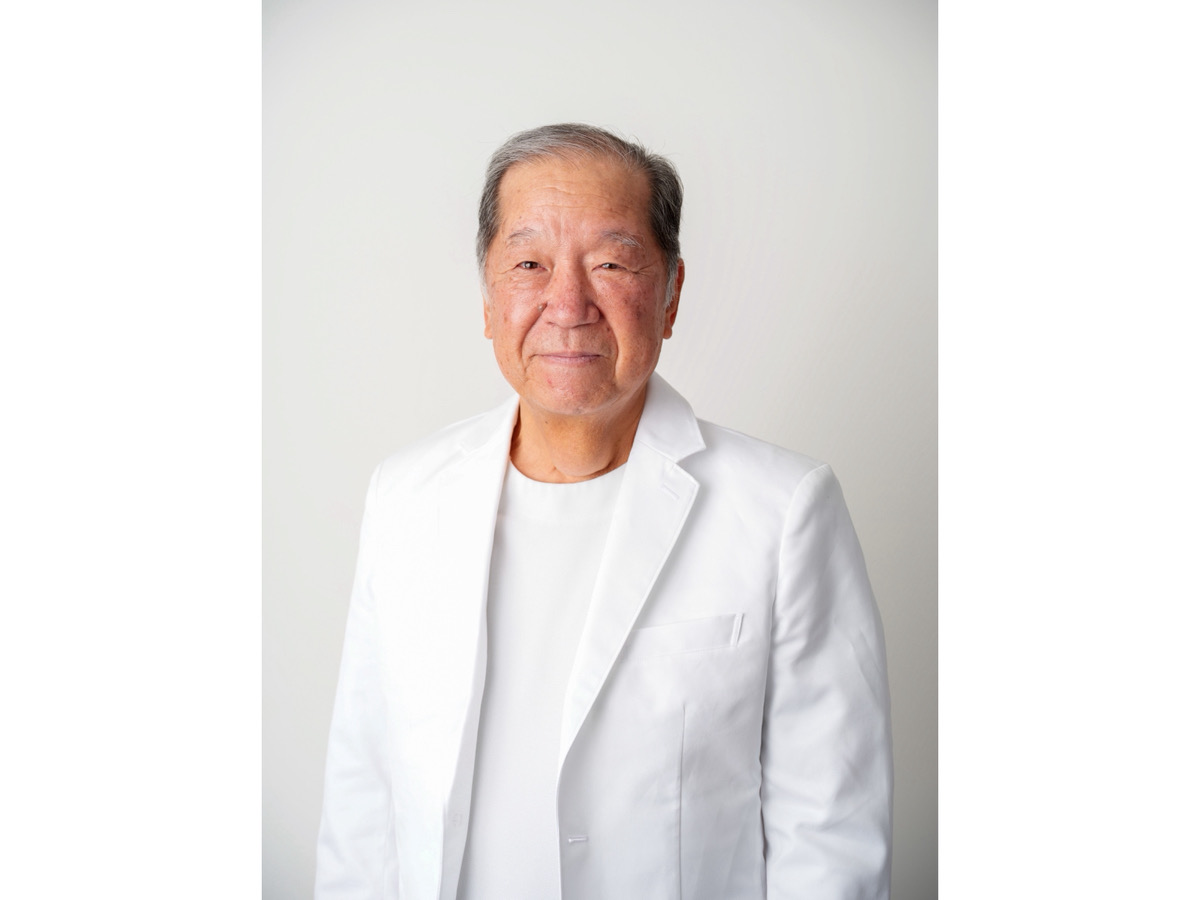
【名誉院長インタビュー前編】真島クリニック――地域に寄り添い、90年。真島クリニックが大切にしてきた『変わらない医療』
名誉院長 医学博士
真島 靖重
真島クリニックは、 不妊治療・妊娠・出産・育児といった人生の大きな転機において、 地域に根ざした“相談しやすい身近な医療機関”としての役割を担っています。 今回の前編では、クリニックの歴史と医療理念、そして培養室や先進医療に対する取り組みについてお話を伺いました。
真島クリニック様は長い歴史を歩まれてきましたが、その中で一貫して大切にされてきた医療理念はどのようなものでしょうか?
私どものこの足立区という地域は荒川・隅田川と大きな川に囲まれた地域ですので、昔から川を越えて受診することが少なく、地元の方が多く受診されていました。
この地域で小児から思春期の悩みや出産はもちろん第二子について、また更年期やシニアにおける婦人科の悩みまで、古くから幅広くあらゆる患者さんに寄り添ってきた歴史があります。
そのため全てのライフステージでの悩みに対応する地域密着型の診療を理念として、その時々の相談に来ていただけるクリニックを目指して診療を行ってきました。
妊娠に関しても、プレコンセプションケアから不妊治療、妊娠~出産・育児までをサポートしたいと考えています。
真島クリニックは75年の歴史ですが、私の母が開業していた助産院時代を含めると90年を超えています。母は助産師として1万例の分娩を、兄は産婦人科医師として分娩、一般不妊治療や人工授精、婦人科診療や開腹手術等を行ってきましたが、ARTをふくめた高度生殖医療を本格的に始めたのは私の代からです。
患者さんの中には、4代続けて「お産は真島クリニックで」と地方から帰産分娩する人もいます。当院で生まれた方が出産に来てくださるようになった時は本当に嬉しく、やりがいを感じました。
地域の方々とのつながりや信頼関係を築く上で、特に意識されていることは何ですか?
意識するというよりも、地域の方が多いので「どこどこの奥さん、おばあちゃんの様子はどうかな」というように話すことが多くなります。お知り合いの紹介で来られる方や先生に(出産を)取り上げてもらったからという方が多く通っています。このような時は近所の人と喋っているような感覚で、自然と親しみが言葉にも出ていると思います。
とはいえ、なかなか医師に伝えにくいという方もいらっしゃいますので、看護師や胚培養士など他職種も含めて対応するようにしています。困ったときに相談に来やすいように、そして悩みを伝えやすいような環境を作ることを心がけています。
不妊治療における「培養室」の体制や工夫、特徴について教えてください。
新築移転となりましたので、培養室の広さや設計は胚培養士の希望を可能な限り取り入れました。動線なども実際に使いやすいように何度も検討し、変更しました。これに際し他のクリニックにいくつも見学に行き、参考にさせていただきました。そして培養室だけでなく、採卵室やガス保管庫なども培養室内の環境のことを考え、工夫をこらしてレイアウトしています。新たにタイムラプスインキュベーターを導入し、先進医療を含め幅広く対応できる培養室となっています。
培養室には精密機器や保管している大事な胚などもありますので、災害時の対策なども見直しています。地震対策として機器の固定などはもちろんのこと、停電の対策として蓄電池システムを設けることにより、対応可能な約14~17時間のあいだに培養している卵などを凍結保存して守る、という対応をとれるようにしています。
さらに、川に囲まれた土地柄から水害も考慮して、クリニックの1階は駐車場とし診療スペースを2階以上にしています。
また、「コウノトリ学級」をはじめとした不妊学級や教育講座やピア・カウンセリングなどを定期的に実施しているのも当院の特徴です。このような学級を通して、ご本人たちが納得する治療を選んでいけるようにと考えています。当院には体外受精コーディネーターが複数名おりますので、治療を進めていく患者さんをサポートさせていただきます。そして、当院の胚培養士は治療中に患者さんに説明を行うことも多くあり、身近な存在であると思います。患者さんが診療中に聞きそびれたことを聞くことができますし、細かな相談にのって医師との間の懸け橋になってくれています。
体外受精・顕微授精など先進医療に取り組まれる上で、特に重視されていることや患者様へのメリットは何でしょうか?
当院では先進医療の登録を多く行っています。そのため、治療の選択肢が増えていることが患者さんへのメリットだと考えています。
先進医療はすべての方に必要な医療ではありませんが、必要な患者さんが必要なものを選択できるという環境を整えて対応していきたいと思っています。
私は子宮内膜細菌叢検査、子宮内膜受用能検査なども積極的に行っています。
初めて不妊治療を受ける方への対応で心がけていることはございますか?
初診時の診察には30分ほどかけています。患者さんからしっかりお話を聞いて、当院での不妊治療の流れを中心に説明しています。初診時にご夫婦で来院される方も多く、お二人に話せるので治療の流れについてなど理解しやすいと思います。その後、体外受精コーディネーターを含めたスタッフからも治療や検査の流れを説明しています。特に仕事や家事との両立、費用や補助金の利用などについても具体的にお話しています。そして、当院の特徴のひとつであるコウノトリ学級などへの参加もお勧めしています。
問題点やお困りごとはご夫婦毎に違うので、それをよく聞いて対応していくように心がけています。看護師・胚培養士などその他のスタッフも説明などで数多く対応しますので、医師に話しにくい場合はその時に相談される方もいます。また、個別にカウンセリングも行っており、ゆっくり時間をかけてお話を聞くこともできます。同じ悩みを共有する方とのピア・カウンセリングも行っていますし、遺伝カウンセラーのカウンセリングを受けることもできます。
困ったらいつでも誰かに相談できるように、当院のスタッフ全員でサポートしていこうと思っています。
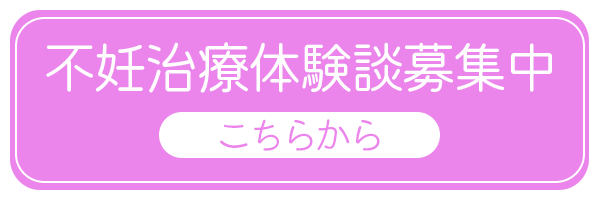
よく読まれている記事

【ニュース】先進医療に「不妊症患者に対するタクロリムス投与療法」が追加

【ニュース・重要】「オビドレル」の出荷停止と今後の見通し

【助成金一覧】東京・神奈川更新のお知らせ

ホームページオープンのご挨拶


 厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ FCHは
FCHは