【コラム】“命のはじまり”を見守る仕事 ― 胚培養士が担う大切な役割
■胚培養とは?
不妊治療において「胚培養(はいばいよう)」とは、体外受精で取り出した卵子と精子を受精させ、受精卵(胚)を数日間培養し、移植に適した状態まで育てる工程 を指します。
つまり、胚培養は「命のはじまり」を院内の培養室で大切に育てる、非常に繊細で専門的な過程なのです。
■胚培養士の役割
この培養の工程を支えるのが「胚培養士(エンブリオロジスト)」です。
医師の指示のもと、採卵で得られた卵子や精子を扱い、
- 受精操作(体外受精・顕微授精)
- 胚の観察・記録
- 凍結保存・融解
- 胚移植の準備
など、命を未来へつなぐ一つひとつの工程を担っています。
胚培養士の世界では「わずかな温度変化」「わずかな時間差」も胚の発育に影響を及ぼすため、正確さ・集中力・経験 が求められます。
顕微鏡越しに、受精卵が分割を重ねていく様子を日々見守りながら、「この小さな細胞が赤ちゃんになる」瞬間を願って業務にあたっています。

■培養の流れと期間
受精卵は、受精の翌日から細胞分裂を始め、2〜5日ほどで「胚盤胞(はいばんほう)」という状態まで成長します。
この培養期間中、胚培養士は顕微鏡で成長過程を観察し、どの胚が最も妊娠につながる可能性が高いか を判断します。
- 3日目:初期胚(細胞が6〜8個ほど)
- 5〜6日目:胚盤胞(細胞数100個以上)
一般的に、この胚盤胞を子宮内へ戻す「胚移植」を行うケースが多くなっています。
ただし、患者さんの年齢や体調、卵巣機能によって最適な培養期間・移植タイミングは異なります。医師・培養士と相談しながら、個々に合ったプランを立てることが大切です。
■近年進む技術の進化
培養環境は年々進化しています。
近年では、タイムラプス培養装置 と呼ばれる機器を導入する施設も増え、胚を取り出すことなくカメラで経過を記録し、発育の過程を連続的に観察できるようになりました。
これにより、胚にストレスを与えず、より正確に「発育の質」を評価できるようになっています。
また、AI技術を応用し、画像解析によって胚の発育を自動評価するシステムも登場しています。
人の経験とテクノロジーが組み合わさることで、より高い精度での胚選別・治療効率化 が期待されています。
■「見えないところ」で支える専門職
患者さんが直接会うことの少ない胚培養士ですが、治療の成否に深く関わる重要な存在です。
培養室の中では、清潔で温度・湿度が厳密に管理された環境のもと、顕微鏡と培養液、インキュベーター(培養器)が静かに稼働しています。
この環境の中で、胚培養士は医師・看護師・カウンセラーらと連携しながら、患者さんの願いを「かたち」にするための裏方として日々努力を重ねています。
■おわりに
胚培養は「見えない命を守る医療」。
顕微鏡の先にある小さな細胞は、未来の家族へとつながる“はじまり”です。
保険適用によって多くの方が治療を選択しやすくなった今こそ、
「どんな人が自分の胚を育ててくれているのか」
「どんな環境で命のはじまりが支えられているのか」
を知ることが、安心と信頼の第一歩につながります。
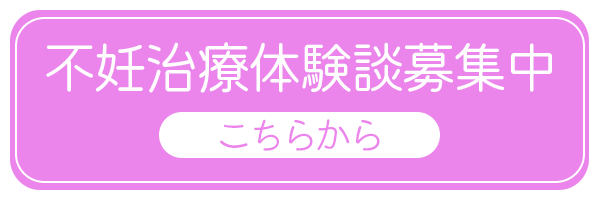
よく読まれている記事

【ニュース】先進医療に「不妊症患者に対するタクロリムス投与療法」が追加

【ニュース・重要】「オビドレル」の出荷停止と今後の見通し

【助成金一覧】東京・神奈川更新のお知らせ

ホームページオープンのご挨拶


 厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ 兵庫県公式サイト
兵庫県公式サイト 兵庫県公式サイト
兵庫県公式サイト







