【コラム】自治体の7割が上乗せ助成──「保険適用」だけでは届かない現実
2022年4月、不妊治療に公的医療保険が適用され、大きな一歩が踏み出されました。
しかし、それは「終わり」ではなく「始まり」にすぎません。
読売新聞が90の自治体を対象に行った調査によれば、全体の約7割が独自に不妊治療への助成を行っていることが明らかになりました。
「保険適用だけでは負担が大きすぎる」
そう判断した自治体が、現場の声に応えるかたちで、支援の手を広げているのです。
当サイト「FCH」でも、日々寄せられる相談の中に、こんな言葉があります。
「保険がきくのはありがたいけれど、実際には自己負担が多く、治療の継続に不安を感じる」
「年齢制限や回数制限に引っかかって、もう助成の対象外になってしまった」
体外受精の1回あたりの費用は、平均で約50万円。
仮に保険が適用されても、3割負担なら15万円。
これが何度も続くとなれば、心身に加えて経済的な負担も計り知れません。
さらに、着床前検査やタイムラプスといった「先進医療」を望めば、保険適用の外となり、全額自己負担となります。
こうした「保険のすき間」を埋める形で、現在62の自治体が上乗せ助成を行っており、先進医療に対する支援、保険適用後の自己負担分への補填、保険対象外となったケースへの助成など、多層的なサポートが進みつつあります。
FCHでは、こうした自治体の支援制度を一元的に探せる「助成金検索サイト」も公開しており、自治体ごとの支援内容を調べることができます。
全国で制度がバラバラな中、「いま自分の住んでいる街でどんなサポートが受けられるのか」を知ることは治療の継続に大きな違いをもたらします。
また、不妊治療にかかわる行政支援のさらなる拡充を求める声も各地で高まっています。
国による制度整備とともに、現場と密接につながる自治体がどのように課題に向き合うか?その姿勢が、これからの医療のあり方を映し出しています。
子どもを望むすべての人に、安心して治療を受ける選択肢を。
その実現に向けて、私たち「FCH」は引き続き、情報発信とサポートの充実に取り組んでいきます。
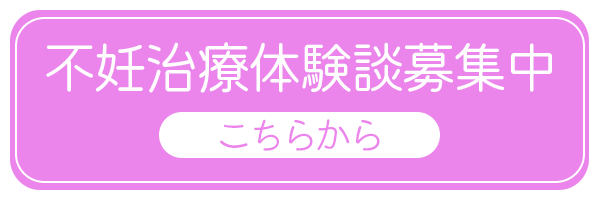
よく読まれている記事

【ニュース】先進医療に「不妊症患者に対するタクロリムス投与療法」が追加

【ニュース・重要】「オビドレル」の出荷停止と今後の見通し

【助成金一覧】東京・神奈川更新のお知らせ

ホームページオープンのご挨拶


 厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ 兵庫県公式サイト
兵庫県公式サイト 兵庫県公式サイト
兵庫県公式サイト







