【コラム】働きながら治療を続ける現実とその工夫
不妊治療に取り組む多くの方にとって、仕事との両立は避けて通れない課題です。
「子どもを授かりたい」という思いと、「今のキャリアを大切にしたい」という思いの間で葛藤しながら、日々を過ごしている人は少なくありません。
実際、当サイトにも「通院が勤務時間と重なってしまう」「治療のたびに仕事を休むのが心苦しい」「治療のスケジュールが予測しづらく、職場に迷惑をかけてしまう」といった声が寄せられています。
今回は、そんな“働きながら治療を続ける現実”に焦点をあて、乗り越えるための具体的な工夫についてご紹介します。
●治療と仕事がぶつかる現実
不妊治療は、一般的に以下のような流れを伴います。
・排卵周期の管理(血液検査・エコー)
・排卵誘発や注射の処置
・タイミング指導、人工授精、体外受精 など
・採卵・移植日程の決定と処置
・判定のための来院
特に体外受精を行う場合、1周期の中で5~10回前後の通院が必要になることもあります。しかも、「次の来院日は排卵の状態を見て翌日に決まる」といった、直前でのスケジュール調整が多く発生します。
一方で職場では、会議や納期、業務分担など、一定の予定と責任を持って日々の仕事が動いています。そこに治療の不確定要素が加わることで、心身ともに大きなストレスを抱える方が少なくないのです。
●治療と仕事を両立させるための具体的な工夫
こうした現実を乗り越えるため、多くの方が自分なりの「工夫」を重ねています。以下にその一部をご紹介します。
①柔軟な働き方を選択する
・テレワークの活用
自宅で仕事ができる環境がある場合は、体調が優れない日や通院前後にも無理なく業務を続けることができます。
・時差出勤やフレックス制度の利用
病院の予約時間に合わせて勤務時間を調整できれば、欠勤せずに治療を継続できます。
②職場の理解を得る
「治療をしていることを職場に話すのが不安」という方は多いですが、信頼できる上司や人事に**「通院が必要である」ことだけでも伝える**と、精神的な負担が軽くなることもあります。
具体的には、
・「一定期間、不規則に半日有休を取る可能性がある」
・「体調や通院の都合で急な調整が発生することがある」
などを伝えるだけでも、働きやすさがぐっと変わります。
また、育児支援が整っている企業でも、不妊治療に関する制度はまだ整っていないケースが多く、従業員から声を上げることが職場全体の改善につながることもあります。
③治療と仕事、どちらも“完璧”を求めない
「仕事を休むのが申し訳ない」
「チームに迷惑をかけたくない」
「治療を優先しているとキャリアに影響するかもしれない」
そんなふうに自分を責めてしまう方も多いですが、治療も仕事も“完璧”でなくて良いのです。少し肩の力を抜きながら、バランスをとっていくことが大切です。
●実際に工夫している方の声
「職場に話すのは怖かったですが、思い切って上司に伝えたところ、通院のための時差出勤を許可してもらえました。相談できたことで気持ちも軽くなり、治療にも前向きに取り組めています」(30代・会社員)
「採卵前後は体調が不安定になるため、有給をうまく組み合わせて、週末に重なるように通院スケジュールを調整。あらかじめ同僚に業務を引き継ぐ準備をしておくことで、安心して休めるようになりました」(40代・専門職)
●社会の理解も、少しずつ進んでいる
2022年の不妊治療の保険適用を機に、企業や自治体でも治療との両立を支援する動きが始まっています。
・不妊治療休暇制度を導入する企業
・治療支援金の支給制度
・治療経験者による社内相談窓口の設置
など、少しずつですが、職場の理解と支援の輪が広がり始めています。
自分らしい選択を、前向きに
働きながらの不妊治療は、体力的にも精神的にも簡単なものではありません。ですが、自分なりの工夫や周囲の理解、社会のサポートがあれば、キャリアも妊活も“自分らしく”続けていくことができます。
FCHでは、こうしたリアルな声や、両立に役立つ制度・情報を今後も発信してまいります。
がんばりすぎず、自分のペースで。
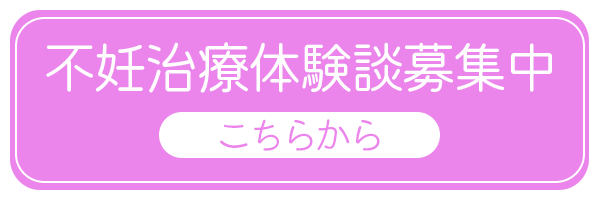
よく読まれている記事

【ニュース】先進医療に「不妊症患者に対するタクロリムス投与療法」が追加

【ニュース・重要】「オビドレル」の出荷停止と今後の見通し

【助成金一覧】東京・神奈川更新のお知らせ

ホームページオープンのご挨拶


 厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ 兵庫県公式サイト
兵庫県公式サイト 兵庫県公式サイト
兵庫県公式サイト







