
【枚方市長インタビュー前編】市の不妊治療支援策について
枚方市長
伏見 隆
現在、枚方市が実施している不妊治療支援の取り組みや、支援を受ける方々の現状について詳しくお伺いしました✨
①現在、枚方市で実施されている不妊治療助成制度の概要を教えてください。
枚方市では、夫婦で受けられた不妊症の検査費用を助成する、「不妊治療ペア検査費用助成事業」を実施しています。
対象は、検査開始日時点で妻の年齢が43歳未満であるご夫婦で、検査開始日から申請日までどちらかが継続して枚方市民であること、夫婦お二人とも検査を受けることが条件となります。婚姻関係につきましては、事実婚の方も対象になります。
対象となる検査は、産婦人科または泌尿器科で、医師が不妊症の診断・治療計画のために必要と認めて行った検査で、検査開始日から1年以内に夫婦お二人が受けた一連の検査です。
助成額は、夫婦一組につき最大5万円助成しています。昨年の4月から助成事業を開始し、今年2月末時点で約85組の方にご利用いただいています。
②なぜ不妊治療のペア検査に関する助成金を施行することになったのか、経緯を教えてください。
不妊治療については、令和4年4月から不妊治療に対する保険適用が拡大され、経済的負担が軽減されました。不妊治療を受ける夫婦は約4.4組に1組と言われており、不妊治療の技術は日々進歩しているところですが、その成功率は年齢とともに下がる傾向があり、早期に治療につながることが重要です。
そこで、将来的に子どもを授かることを希望する夫婦を対象に、夫婦そろって早期に不妊検査を受け、不妊の原因を発見し、必要に応じて適切な治療を始められるよう、不妊検査に要する費用の助成を開始しました。
検査費用を助成することで、子どもを望むご夫婦が不妊治療に取り組みやすい環境づくりにつながればと思っております。
③不妊治療を受ける方々へのサポートとして、特に力を入れているポイントは何ですか?
不妊治療ペア検査費用助成事業では、夫婦ペアで受けていただいた検査を対象としています。不妊というと女性不妊を連想する人もおられますが、実際には不妊の約半数は男性にも原因があることが分かっています。不妊に関する心配ごとには夫婦で取り組んでいただけるよう、ペアでの検査を費用助成の要件とさせていただいております。
また、本事業では、不妊症の診断や治療計画のために医師が必要と認めた検査であれば、保険適用の有無に関わらず、検査にかかった費用の自己負担分について助成しています。
不妊治療には、仕事との両立や周囲の理解などまだまだ課題もありますが、市が不妊治療につながる検査費用を助成することで、後押しができるよう、少しでも不妊治療に取り組みやすい社会をつくっていくことができればと考えています。
また、これは枚方市役所の制度なのですが、枚方市役所でも一事業所として、市役所に務める職員の不妊治療を支援する「出生サポート休暇」を設けています。これは、職員が不妊治療のための通院などをする場合に認められる休暇で、週5日勤務の正職員や任期付職員などで、1年度につき5日以内、頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は10日以内を認めています。こうした制度を設けることで、職場においても、不妊治療を受けやすい環境づくりをサポートしていきたいと考えています。
④枚方市には不妊治療を行っておられるクリニックがたくさんありますが、そうした医療機関とどのように連携していきたいと考えておられますか?
不妊治療ペア検査費用助成事業の開始に当たっては、市内のクリニックをはじめ大阪府内で不妊治療を行っているクリニックにアンケート調査を行い、ご意見を参考にさせていただいたほか、事業開始の際には案内チラシを送付させていただきました。
お蔭をもちまして、クリニックで本市の制度を紹介されて、助成を申請した方も多くおられます。せっかく支援する制度を構築しても必要とする人に情報が届かなければ意味がありませんので、医療機関から対象となる人にご紹介いただけているのは、とても有難いことだと思っています。
今後も、力をお借りしながら、子どもを望むご夫婦を支えるまちづくりを進めていきたいと考えています。
⑤助成対象外となる治療や費用について、今後拡充する予定はありますか?又、市の予算等あるかとは思いますので、国の補助金制度の中に是非今後組み込んでほしいとお考えのものはございますか?
本市では、不妊治療ペア検査の他にも、不育症の検査と治療への助成事業を行っています。妊娠はするものの流産等を繰り返す不育症にお悩みのご夫婦を支援するもので、いずれも所得制限や年齢制限を設けず、費用を助成しています。
検査費用の助成としましては、不育症の原因検索のために受けた検査のうち、リスク因子に係る検査は1回につき最大5万円、同じ年度内に2回以上申請される場合は1年度につき上限5万円、先進医療の検査は1回につき費用の7割に相当する額を最大6万円助成しています。
治療費用の助成としましては、医療保険が適用されない不育症治療費について、一年度につき30万円を上限に助成しています。
不育症検査費用の助成は令和6年1月より、不妊治療ペア検査費用の助成は令和6年4月より開始したところでもありますので、助成対象外となる治療や費用については、今後、国などの動向を注視していきたいと思っております。
国に対しては、不妊検査や不育治療等を含め、医療保険の適用範囲の拡充については柔軟に対応していただきたいことと、全国各地で行われている不妊治療や検査等への助成の実態を踏まえ、医療保険の適用から外れる範囲については、全国統一的な新たな助成制度の構築について検討していただきたいと考えております。
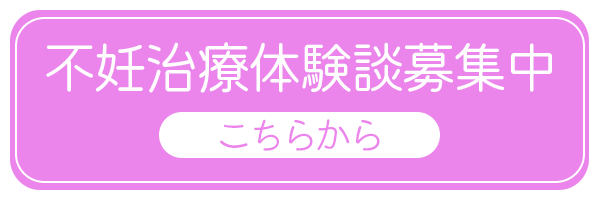
よく読まれている記事

【ニュース】先進医療に「不妊症患者に対するタクロリムス投与療法」が追加

【ニュース・重要】「オビドレル」の出荷停止と今後の見通し

【助成金一覧】東京・神奈川更新のお知らせ

ホームページオープンのご挨拶


 厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ FCHは
FCHは








