
【理事長インタビュー】ファティリティクリニック東京――培養技術と人の力で“個別化医療”を支える
理事長 医学博士
小田原 靖
培養技術の正確さを追求しながら、患者様一人ひとりに寄り添った治療を行う―― 今回は、ファティリティクリニック東京の小田原理事長に、その想いや取り組みについてお話を伺いました✨
ファティリティクリニック東京様ならではの強み・特色を教えてください。
不妊治療、いわゆる生殖医療・生殖補助医療においては、体外環境での培養操作が治療の基盤となります。そのため、培養技術の正確さと信頼性は極めて重要です。当院では高い技術力を有し、全スタッフがその意識を共有しています。
生殖医療は工業製品のように均一化された工程ではありませんので、患者様一人ひとりの体質や背景により、最適な治療法が異なります。そのため、個別に「何が必要か」を見極める“個別化医療”を重視しています。お一人おひとりに必要な治療を丁寧に見極め、全力で最善を尽くす姿勢が当院の強みであり、この考え方は全ての医師やスタッフに浸透しています。
年齢や背景が異なる患者様に合わせた“オーダーメイドの治療方針”については、どのような工夫がありますか?
現在、不妊治療を行うクリニックは全国に多数あり、自然周期や低刺激周期などさまざまな方法が取られています。それぞれに特徴がありますが、当院では画一的な治療を繰り返すのではなく、患者様の反応や治療経過をもとに原因を探り、次の一手を常に考えています。
保険診療の範囲では制限が多いものの、必要に応じて先進医療や大学機関との検査、自費でのPGT-A(着床前胚異数性検査)なども組み合わせながら、最適な治療を提案しています。年齢が上がるにつれ、卵巣機能やホルモン環境などが変化するため、同じ方法を繰り返しても同じ結果が得られないことが多いのが現実です。
たとえば卵巣刺激に使用する薬剤一つを取っても、患者様ごとに相性があります。薬の種類や量、培養日数、受精方法など、あらゆる要素を個別に最適化することが重要です。当院では、この「個別最適化」を徹底し、治療効果を最大化することを目指しています。
治療に伴う心理的負担や不安に対して、どのようなカウンセリング・サポート体制を整えていらっしゃいますか?
不妊治療は身体的な負担だけでなく、心理的なストレスも大きいものです。当院では、心理的サポートの必要性を重視し、専任カウンセラーによる心理カウンセリングを実施しています。治療が思うように進まない時期や、結果が出ずに気持ちが落ち込むときなどに、少しでも患者様の支えとなれるよう体制を整えています。
不妊治療の保険適用拡大によって、実際の臨床現場や患者動向にどのような変化がありましたか?
2022年から不妊治療が保険適用となり、以前の助成金制度に比べて患者様の自己負担が軽減されました。その結果、比較的若い世代の方々が治療を早期に始めるケースが増加しています。若年層での治療成績は良好であり、早期の妊娠・出産や受精卵凍結による将来への備えが進んでいる点は非常に良い傾向です。
一方で、保険適用による制約も少なくありません。採血や薬剤の使用量・種類などに制限があり、特に年齢が高く治療が難航する方々に必要な検査(例:PGT-A)や治療法の多くが保険適用外となっています。そのため、保険の回数上限に達すると治療を断念される方も増えており、今後の課題と考えています。
JISART認定やISO 9001認証など、品質保証の取り組みを続けてこられた背景を教えてください。
当院では、医療品質の継続的な向上を目的に、JISART認定およびISO 9001認証を取得しています。これらの制度は、体外受精など高度な生殖医療を安全かつ正確に行うための国際的基準に基づくものであり、外部監査による定期的な評価を受けています。
日本では保険適用拡大後、施設の技術レベルを公的に評価・認定する仕組みが乏しいのが現状です。そのため当院では、早くから品質保証の仕組みを取り入れ、スタッフの教育体制や培養士の技術評価、患者満足度調査など、あらゆる面で外部監査を受けてきました。これにより、スタッフが入れ替わっても安定した医療を維持できる体制を整えています。
こうした取り組みは2000年頃から始まり、20年以上にわたり継続しています。JISARTおよびISOによる外部審査を3年ごとに受け、全ての業務プロセスやマニュアルを開示して改善を重ねてきました。この積み重ねが、当院の信頼性を支える大きな柱となっています。
日本のART医療における課題や、今後必要とされる政策についてお聞かせください。
日本の不妊治療における大きな課題のひとつは、保険診療の範囲内では個々の患者様に最適な治療が行いにくい点です。財源の制約上、治療内容が標準化されており、個別対応が難しい場面が多々あります。そのため、一定の範囲で混合診療を認める仕組みが必要だと考えています。
特に、年齢が高く治療が長期化している方に対しては、保険診療だけでは限界があります。保険終了後に助成金や個別支援制度などを整備し、患者様が納得のいく形で治療を継続できるような政策が求められます。
海外の生殖医療との比較や、今後の国際的な連携への展望をお聞かせください。
日本の生殖医療は、技術面では非常に高い水準にあります。特に胚の凍結技術や精密な操作技術は世界的にも評価されています。一方で、日本では施設の規模が小さいことや倫理的制約の違いにより、国際的な連携や研究体制の整備が難しいという課題があります。
また、ドナー提供(卵子・精子)や第三者間治療に関しては、法的・倫理的な枠組みが国によって大きく異なります。日本では依然として制約が多く、治療を希望する方が海外で治療を受けるケースもあります。今後は、倫理性と安全性を両立させながら、国際基準に近い治療体制を整備していくことが望まれます。
AIやデジタル技術が生殖医療に導入されていく可能性についてお考えをお聞かせください。
AIやデジタル技術の発展により、培養システムや顕微授精の自動化が今後さらに進むと予想されます。現在では、患者様への情報共有や治療説明の場面でデジタルツールが活用されることも増えています。
また、AIによる翻訳・通訳技術の進歩により、外国人患者様にとっても受診していただきやすい環境が広がっていきます。こうした技術の導入は、医療現場の効率化だけでなく、患者様がより安心して理解を深められる体制づくりにもつながっていると考えています。
若年層に向けたプレコンセプションケアの取り組みについてのお考えをお聞かせください。
プレコンセプションケア(妊娠前の健康管理)は非常に重要です。妊娠には年齢的な限界があることや、妊娠を妨げる可能性のある要因について若いうちから正しい知識を持つことが大切です。当院ではブライダルチェックやプレコン相談を行い、将来の妊娠に備えるための支援を行っています。
「治療」というと敷居が高い印象を持つ方も多いですが、「プレコン」という入り口であれば気軽に検査や相談ができることから、近年では相談件数も増加しています。この流れは非常に良い傾向だと考えています。
今後取り組んでいきたい挑戦や、読者に伝えたいメッセージをお願いいたします。
今後も、学術的な研究や臨床研究を通じて新しい知見を積み重ね、治療の有効性を高めていくことを目指しています。保険診療体制の中では研究活動が制約される場面もありますが、小さな取り組みからでも前進を続けたいと考えています。
また、患者様にお伝えしたいのは、医療機関との「相性」を大切にしてほしいということです。どのクリニックにも特色があり、最も重要なのは“人が人を診る”という信頼関係です。当院ではオンライン相談も実施しており、診療前に女性医師との面談なども可能です。時間や状況に合わせて、安心して相談できる環境を整えています。
患者様の努力や想いに寄り添い、妊娠・出産を迎えられた際の喜びを共有できることが、私たちの何よりの原動力です。その瞬間のために、これからも全力を尽くしてまいります。
多様な患者様に対して、最適な治療を見極めるための「個別最適化」を徹底されている姿勢が印象的でした。 FCHでは、今後も医療現場からの“妊娠・出産に寄り添う想い”を発信してまいります✨
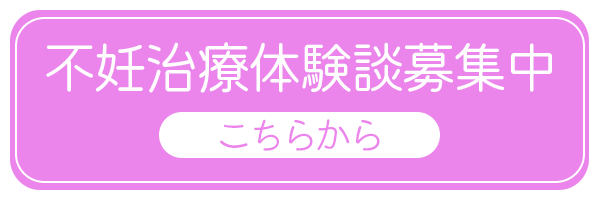
よく読まれている記事

【ニュース】先進医療に「不妊症患者に対するタクロリムス投与療法」が追加

【ニュース・重要】「オビドレル」の出荷停止と今後の見通し

【助成金一覧】東京・神奈川更新のお知らせ

ホームページオープンのご挨拶


 厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ FCHは
FCHは








